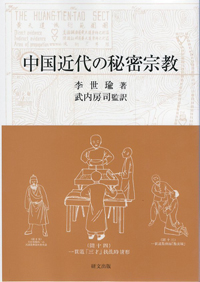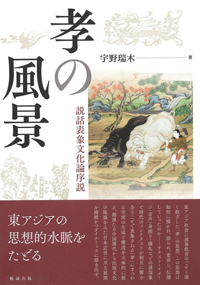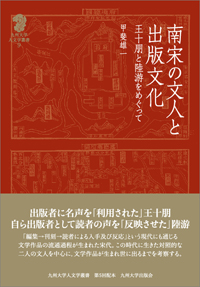日韓近期漢學出版物(十七)
2016·2——2016·
1、中國近代の秘密宗教
時 間:2016年3月
作 者:李世瑜 著,竹內房司 監譯
出版單位:東京:研文出版
內容簡介:
緒論
第1章 黃天道
第1節 萬全県における黃天道の発見
第2節 萬全県における黃天道の流伝范囲
第3節 普明仏の伝說
第4節 黃天道経典研究
第5節 教義と儀禮
第6節 明代の黃天道
第2章 一貫道
第1節 一貫道源流考證
第2節 一貫道宣伝方法
第3節 一貫道の教義の紹介
第4節 一貫道儀禮規則について
第5節 一貫道経典提要
第3章 皈一道
第1節 皈一道の歴史
第2節 皈一道信者の生活
第3節 皈一道の教義の概要
第4節 皈一道の修行規則
第5節 皈一道経典提要
第4章 一心天道龍華圣教會
第1節 一心天道龍華圣教會の概要
第2節 1951年の一心天道龍華圣教會調査
第5章 天津在理教調査報告
第1節 在理教の源流
第2節 在理教の活動
第3節 在理教の信仰·修練·規范
第4節 在理教の斎口
2、孝の風景:說話表象文化論序說
時 間:2016年3月
作 者:宇野端木 著
出版單位:東京:勉誠出版
內容簡介:
序論
第一部 図像の力
はじめに——墓と図像
第一章 后漢墓における孝の表象——山東省嘉祥県武梁祠畫像石を中心に
第二章 六朝時代以降の孝子図——墓における復數の世界観と孝との融合
第三章 孝子伝図から二十四孝図へ——遼·宋代以降を中心に
結
第二部 語りの生起する場
はじめに——今ここを現出する力
第四章 郭巨說話の母子像——唐代仏教寺院における唱導を中心に
第五章 郭巨說話の「母の悲しみ」——日本中世前期の安居院流唱導を中心に
第六章 日本中世の追善供養の場と孝子說話——『金玉要集』の孟宗說話を中心に
結
第三部 出版メディアの空間
はじめに―視覚時代の幕開け
第七章 和制二十四孝図の誕生——日中韓の図像比較から
第八章 蓑笠姿の孟宗——日本における二十四孝の絵畫化と五山僧
第九章 江戸期における二十四孝イメージの泛濫/反亂——不孝、游戲を契機として
結
結論 孝の表象——波うち際にて
3、中國現代散文杰作選:1920-1940 戦爭、革命の時代と民眾の姿
時 間:2016年3月
作 者:中國一九三〇年代文學研究會 編
出版單位:東京:勉誠出版
內容簡介:
命·時代
魯迅「劉和珍君を記念する」
丁玲「三八節有感」
孫犁「采蒲臺の葦」
聞一多「儒·道·土匪について」
費孝通「復讎は勇に非ず」
茅盾「故郷雑記」
旅·異郷
夏卞尊「日本の障子」
瞿秋白「赤いロシアの帰り道」
徐志摩「我が心のケンブリッジ」
艾蕪「茅草地で」
簫紅「東京にて」
馮至「山村の墓碑」
鄭振鐸「海燕」
郁達夫「還郷記」
故郷·民眾
蘆焚「紅廟行」
何其芳「弦」
朱光潛「人生と自分について」
徐蔚南「山陰道上」
梁実秋「雅舎」
周作人「水の中のもの」
巴金「エルクの燈火」
呉組湘「薪」
兪平伯「陶然亭の雪」
家族·生命
朱自清「后ろ姿」
老舎「私の母」
凌叔華「愛犬ぶちを悼む」
豊子愷「おたまじゃくし」
沈従文「街」
李広田「花鳥おじさん」
廃名「秋を悼む」
謝冰心「南帰」
4、蔣介石の「國際的解決」戦略:1937-1941「蔣介石日記」から見る日中戦爭の深層
時 間:2016年2月
作 者:鹿錫俊 著
出版單位:東京:東方書店
內容簡介:
第1章 「國際的解決」戦略の論理と日中戦爭の長期化
第2章 危機と転機、そしてヨーロッパ情勢への対応
第3章 獨ソ不可侵條約とヨーロッパ戦爭開戦をめぐって——日記から見る蔣介石の政策決定過程
第4章 「二つの同時」論と「世界的規模収拾策」——異なる「國際的解決」戦略の交錯
第5章 援中ルート閉鎖期間の試練——1940年夏における対獨·対日政策の再選択
第6章 日獨伊三國同盟をめぐる多角外交
第7章 獨ソ戦爭への予測と対處
第8章 日米交渉期の攻防——日本の対応と蔣介石の反応
終章 蔣介石外交の評価
5、近代アジア市場と朝鮮:開港·華商·帝國
時 間:2016年3月
作 者:石川亮太 著
出版單位:名古屋:名古屋大學出版會
內容簡介:
序章 近代アジア市場の中の朝鮮開港——華商からのアプローチ
第Ⅰ部 朝鮮開港と華商ネットワークの延伸
第1章 開港場をめぐる移動と制度の相克——釜山日本居留地における華人居住問題
第2章 在朝日本人商人と華商からの 「自立」——海產物の対中國輸出をめぐって
第3章 伝統的陸路貿易の連続と再編——1880年代の紅蔘輸出と華商
第4章 華商の対朝鮮人取引と紛爭處理——ソウルにおける訴訟事例から
第Ⅱ部 朝鮮華商の貿易と多角的ネットワーク——広東商號同順泰の事例分析
第5章 同順泰の創設とネットワーク形成
第6章 同順泰の対上海貿易と決済システム——日清戦爭前を中心に
第7章 同順泰の內地通商活動とその背景
第8章 深化する日朝關系への対応——日清戦爭后の同順泰
補論 同順泰文書について
第Ⅲ部 帝國への包摂·帝國からの漏出——日露通貨の広域流通と華商
第9章 近代アジア市場の中の朝鮮地方経済——ルーブル紙幣の広域流通を通じて
第10章 日本の満洲通貨政策の形成と対上海關系——日露戦爭軍票の流通実態
第11章 植民地化前后の朝鮮華商と上海送金——朝鮮銀行券の循環に與えた影響
第12章 1910年代の間島における通貨流通システム——朝鮮銀行券の満洲散布と地方経済の論理
終章 朝鮮開港期の歴史的位相——華商ネットワークが作る 「地域」
6、唐代の文學理論:「復古」と「創新」
時 間:2016年3月
作 者:成田健太郎 著
出版單位:京都:京都大學學術出版會
內容簡介:
序章
第一節 書學理論の定義とその研究の意義
第二節 中古における書學理論の発達
第三節 本書の取り扱う書學理論著作
第四節 書學理設研究の方向と本書の達成
第一章 書體を詠う韻文ジャンル「勢」とその周辺
第一節 「勢」というジャンル
第二節 「勢」の様式
第三節 趙壱「非草書」にみる「勢」の胎動
第四節 「勢」と詠物賦
第五節 「勢」の形成と展開(東晉まで)
第六節 劉宋以降の「勢」と散文書論
第七節 小結
附録 十家勢輯校
第二章 張懐瓘『書斷』の書體論
第一節 張懐瓘『書斷』の品第法と書體論
第二節 『書斷』の十體
第三節 質と文、古と今
第四節 靜と動
第五節 篆隸における書體論
第六節 草隸における書體論
第七節 『書斷』の書體論の成果
附表
第三章 張懐瓘『書斷』の史料利用と通俗書論
第一節 『書斷』の史料利用に關する先行研究
第二節 『書斷』の史料利用の體例
第三節 正統書論と通俗書論
第四節 『書斷』の通俗書論利用
第五節 『書斷』と通俗書論の接近
第六節 小結
第四章 初唐以前の書訣について
第一節 緒論
第二節 材料の整理
第三節 問題點の検討
第四節 余論·小結
第五章 魏晉南朝の文論·書論にみる風格論と技法論
第一節 人物評論にみる風格論とその文論への展開
第二節 魏晉南朝の書論にみる技術と風格
第三節 文體·書體の別と筆勢の位置
第四節 風格から技法へ
第六章 〈筆勢〉の生れるところ
第一節 緒論
第二節 〈勢〉の構造
第三節 書論における〈勢〉
第四節 筆の形象
第五節 書論における筆と〈筆勢〉
第六節 書訣における筆法と〈筆勢〉
第七節 小結
7、「心身/身心」と環境の哲學 新刊——東アジアの伝統思想を媒介に考える
時 間:2016年3月
作 者:伊東貴之 著
出版單位:東京:汲古書院
內容簡介:
日文研の共同研究會と本論集の趣旨(伊東貴之)
第一部:東アジアの伝統的な諸概念とその再検討の試み
朱熹の「敬」——儒教的修養法の試み(土田健次郎)
心學としての朱子學——朱熹の「理」批判と経學(垣內景子)
袁仁『砭蔡編』について——明代における蔡沈『書集伝』に対する批判の特例(陳健成)
陽明后學の講學活動と日常——鄒守益の詩文より見たる(永冨青地)
仇兆鰲と內丹修錬——儒教と道教のはざまで(橫手裕)
阮元「論語論仁論」の評価をめぐって(林文孝)
朝鮮思想再考(権純哲)
〈悪〉とは何か——本居宣長『古事記伝』の場合(田尻佑一郎)
江戸后期の文獻研究と原典批判(竹村英二)
清代経世思想の潮流——経世學と功利學(大谷敏夫)
第二部:心と身體、環境の哲學——東アジアから考える
仏教における身體性の問題——キリスト教との対比から(末木文美士)
「易」の環境哲學(桑子敏雄)
拡張した自己の境界と倫理(河野哲也)
中國醫學における心身關系(長谷部英一)
跪拝の誕生とその変遷(西澤治彥)
唐初期唯識思想の人間本質観(橘川智昭)
「心」と「身體」、「人間の本性」に關する試論——新儒教における哲學的概念の再検討を通じて(伊東貴之)
全真教における志·宿根·圣賢の提挈——內丹道における身體という場をめぐって(松下道信)
江戸期における物心二元論の流入と蘭學者の心身観(フレデリック·クレインス)
近世日本における武道文化とその身心修行的性格——中國·朝鮮の武術との比較を踏まえて(魚住孝至)
神津仙三郎『音楽利害』の音楽療法思想にみる東洋的身體観(光平有希)
孔子の祭りに牛·山羊·豚は不要か?——中華文化復興運動期の臺灣における「禮楽改革」事業の一斑(水口拓壽)
日本人の空気観——電気、空気、雰囲気という漢語をめぐって(新井菜穂子)
自然環境と心=身問題のために——概念操作研究の勧め(鈴木貞美)
日本仏教における身體と精神、キリシタン時代の霊魂論の問題をめぐって(フレデリック·ジラール)
第三部:思想·宗教·文化がつなぐ/むすぶ東アジア——文化交流と文化交渉の諸相
東アジアの南北半月孤(高橋博巳)
正気歌の思想——文天祥と藤田東湖(小島毅)
高麗と北宋の仏教を介した交渉について——入宋僧を中心に(手島崇裕)
太鼓腹の彌勒は仏教なのか——布袋和尚伝記考(陳継東)
新井白石の漢學と西學——朱子學的「合理主義」と真理概念の普遍性において(李梁)
「教化」から「教育」と「宗教」へ——近世·近代日本における「教」の歴史(鍾以江)
梁啟超の「幕末の陽明學」観と明治陽明學(李亜)
「宗教」としての近代日本の陽明學(山村奨)
民國知識人の文化自覚と伝統——梁漱溟の「東方化」の再解釈を兼ねて(銭國紅)
日中道義問答――日米開戦后、「道義的生命力」を巡る占領地中國知識人の議論(關智英)
二十世紀初頭、安岡正篤の日本主義のおける直接的行動主義——安岡正篤のベネデット·クローチェ訪問計畫に留意して(竹村民郎)
吉田松陰の革命思想とその天下観(楊際開)
8、南宋の文人と出版文化:王十朋と陸游をめぐって
時 間:2016年3月
作 者:甲斐雄一 著
出版單位:福岡:九州島大學出版會
內容簡介:
序章
一 宋代文人と版本の普及
二 南宋出版文化における地域性
三 士大夫と中間層文人
四 王十朋と陸游
五 關連する先行研究の概要
六 本書の構成と目的
上篇 「狀元」王十朋と南宋出版業
第一章 王十朋編『楚東唱酬集』について 南宋官僚文人の地方赴任と出版
第二章 王十朋『會稽三賦』と史鋳注
第三章 「王狀元」と福建 王十朋と『王狀元集百家注東坡先生詩』の注釈者たち
下篇 陸游の四川體験と『剣南詩稿』の刊刻
第四章 陸游と四川人士の交流 范成大の成都赴任と關連して
第五章 陸游の厳州赴任と『剣南詩稿』の刊刻
第六章 南宋の陸游評価における入蜀をめぐって,宋代杜甫詩評を手がかりとして
終章
一 集注本、詩話総集と中間層文人の諸相
二 中間層文人と江湖詩人
三 南宋文化の地域的偏差